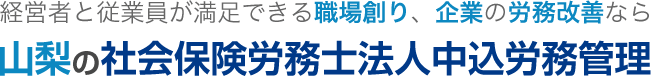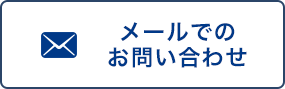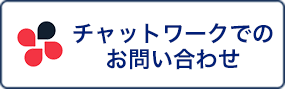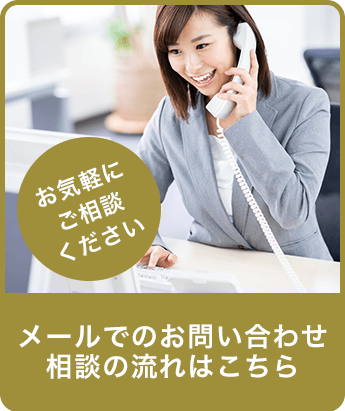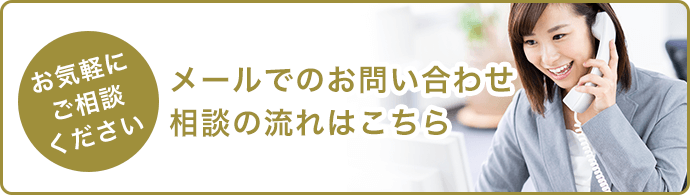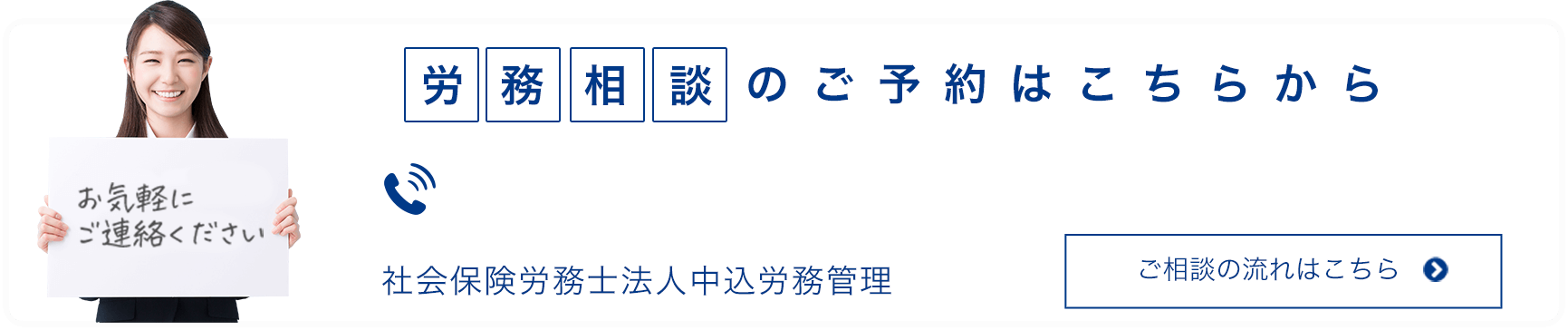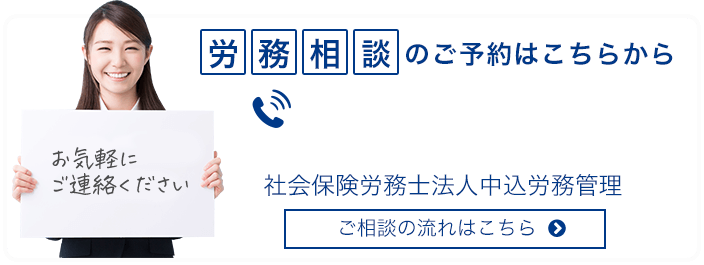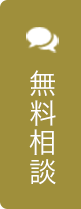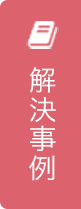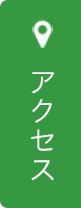人事・労務ジャーナル 2025年5月
- 2025.05.03 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
01 新時代を牽引するZ世代!デジタルネイティブの特徴と企業成長を促す育成戦略
今回は、企業の未来を担う「Z世代」にスポットを当て、その特徴や効果的な育成戦略について解説します。Z世代はデジタルネイティブとして生まれ育ち、既存の常識にとらわれない柔軟な思考を持つ一方、従来世代との価値観の違いから、組織内でのコミュニケーションや育成が難しいと感じられることもあります。企業としてはZ世代を適切に理解し、スムーズに成長をサポートすることで、組織力の向上や新たなイノベーションの創出に繋がります。
02 テレワーク義務化?2025年改正 育児・介護休業法の柔軟勤務策を解説
4月の育児・介護休業法の改正は、育児や介護と仕事を無理なく両立できる社会を実現するための大きな一歩とされています。少子高齢化の影響で人材確保が難しくなる中、中小企業においては、従業員の柔軟な働き方をどのように整備するかが重要な課題です。この改正ではテレワークの導入が大きな注目を集めており、在宅勤務や時差出勤、短時間勤務などの制度を積極的に取り入れることで、従業員が安心して働ける環境づくりを進めることが求められます。
新時代を牽引するZ世代!デジタルネイティブの特徴と企業成長を促す育成戦略
今回は、企業の未来を担う「Z世代」にスポットを当て、その特徴や効果的な育成戦略について解説します。Z世代はデジタルネイティブとして生まれ育ち、既存の常識にとらわれない柔軟な思考を持つ一方、従来世代との価値観の違いから、組織内でのコミュニケーションや育成が難しいと感じられることもあります。企業としてはZ世代を適切に理解し、スムーズに成長をサポートすることで、組織力の向上や新たなイノベーションの創出に繋がります。
Z世代はこんな世代
Z世代とは、主に1990年代後半から2000年代前半に生まれた世代を指し、物心がついたときからインターネットやSNSが身近に存在していました。そのため、情報収集力が高く、デジタルツールを使いこなすことに長けているのが大きな特徴です。また、SNSを通じて常に多様な価値観に触れているため、「共感」や「透明性」、そして「多様性」を重視する傾向が強いといわれています。しかし、SNSがコミュニケーションの主流になっていることから、直接コミュニケーションを取ることが苦手な方も少なくないです。
Z世代の強みと組織への影響
Z世代は、柔軟な発想と変化への適応力を持つ一方で、自己表現の機会を大切にする世代でもあります。新しいアイデアや視点を積極的に取り入れる姿勢は、組織に新たな風を吹き込み、停滞していた業務プロセスの見直しやデジタル化を加速させる可能性があります。ただし、画一的な管理や古い慣習が続く環境下ではモチベーションが下がりやすく、結果的に離職率が高まるリスクもあるといえます。そのため、彼らの得意分野を伸ばしつつ、本人たちが共感できるように会社のミッションやビジョンをわかりやすく伝えることが重要です。
Z世代を育成・定着させる3つのポイント
1つ目は「コーチング型コミュニケーションの導入」です。上司からの一方的な指示ではなく、対話を通じてコミュニケーションをとることで気づきを与え、主体的な行動を引き出すことができるでしょう。2つ目は「デジタルツールやオンライン学習の積極活用」。Z世代は新しいツールを素早く取り入れられるため、eラーニングやクラウドを使った研修環境を整えると、効率的にスキルを習得できます。3つ目は「多様な働き方や評価基準の導入」です。個々の強みやライフスタイルを考慮した柔軟な制度を用意することで、メンバーが長期的に組織に貢献しやすくなるでしょう。
Z世代はデジタルを活用するスキルと多様性を受け入れるマインドを兼ね備えた、企業の新たな成長エンジンとなり得る世代です。画一的な管理や指示に頼るのではなく、コーチング型のコミュニケーションや柔軟な制度設計によって、Z世代のクリエイティビティとモチベーションを引き出すことがポイントになります。皆さんの職場でも、彼らが力を発揮しやすい環境を整え、新しい価値を生み出す風土を育んでいきましょう。
若年労働者を定着させる!効果的な対策とは?
4月の育児・介護休業法の改正は、育児や介護と仕事を無理なく両立できる社会を実現するための大きな一歩とされています。少子高齢化の影響で人材確保が難しくなる中、中小企業においては、従業員の柔軟な働き方をどのように整備するかが重要な課題です。この改正ではテレワークの導入が大きな注目を集めており、在宅勤務や時差出勤、短時間勤務などの制度を積極的に取り入れることで、従業員が安心して働ける環境づくりを進めることが求められます。
テレワーク導入の背景と育児への影響
法改正の背景には、出産や育児に伴う離職を少しでも減らしたいという社会的なニーズがあります。特に子どもの保育園探しや育児との時間調整が難しい中、出勤にかかる通勤時間を削減できるテレワークは大きな役割を果たします。今回の改正では、小さい子どもを育てる従業員に対して在宅勤務の導入をはじめとした柔軟な働き方を選択できるよう制度を整備することが、事業主の新たな義務として盛り込まれました。柔軟な働き方が可能になれば、育児休業の取得率向上や早期離職防止にもつながり、人材の確保と定着の両面で企業にメリットが生まれると期待されています。
介護と仕事の両立支援はどう変わる?
育児だけでなく、介護についても同様に柔軟な働き方を取り入れることが強く求められます。親や家族の介護が必要になる時期は予測が立てにくく、急な離職につながるリスクが高いとされてきました。そこで、今回の改正では介護を抱える従業員にもテレワークの導入をし、無理なく働き続けられるようにすることが企業の努力義務とされました。早めに制度を整え、相談窓口や研修の機会を設けることで、従業員が不安を感じずに業務を継続できる環境づくりを進めることが大切です。
中小企業が実務で押さえるポイント
まずは就業規則や社内規程を見直し、育児・介護休業の取得条件や手続き方法、テレワークを含む柔軟勤務制度の利用範囲を明確にしておくことが重要です。業務の性質上、在宅勤務が難しいケースもありますが、ハイブリッド勤務や時差出勤など可能な手段を組み合わせることで、多様な働き方を確保することは十分に可能です。また、法改正により義務づけられる個別の意向確認や周知の手続きにも対応できるよう、人事担当者への研修やマニュアル整備を進める必要があります。助成金制度や行政の相談窓口など、活用できる支援策も積極的に調べ、導入コストや手間を抑えながらスムーズに新制度へ移行しましょう。
今回の改定では在宅勤務や時差出勤、短時間勤務などの制度を積極的に取り入れることで、従業員が安心して働ける環境づくりを進めることが求められています。社内の体制を早めに見直し、既に改定された法律の趣旨を理解したうえで対応を進めましょう。
-
社会保険労務士法人労務管理PLUSへの
人事と労務管理の専門家として、これまで各業種の企業さまへさまざまなサポートを提供してまいりました。顧問企業がお困りの際に「受け身」でご支援を行うだけではなく、こちらから「積極的に改善提案を行うコンサルティング業務」をその特色としております。人事労務にお悩みのある企業さまはもちろんのこと、社内環境の改善を目指したい方、また問題点が漠然としていてご自身でもはっきり把握されていない段階であっても、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。
最新のお知らせ・セミナー情報
-
- 2026.02.04 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「労働基準法の改正議論を解説!企業が今から備えるポイント!」をお送りします❗️
-
- 2026.02.03 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 人事・労務ジャーナル 2026年2月
-
- 2026.01.19 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「カスハラ対策義務化で企業が取り組むべき対応!」をお送りします❗️
-
- 2026.01.16 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「2026年以降に拡大する社会保険適用のポイント!」をお送りします❗️
-
- 2026.01.05 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 人事・労務ジャーナル 2026年1月