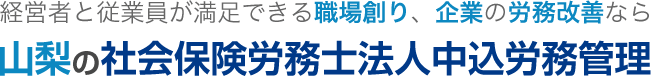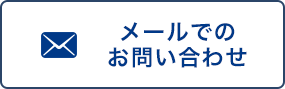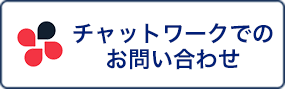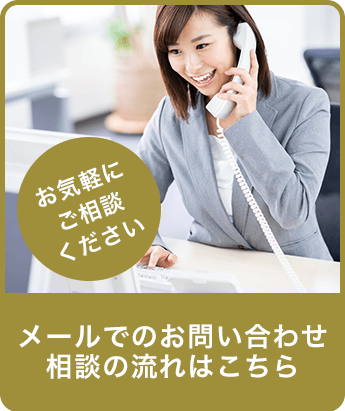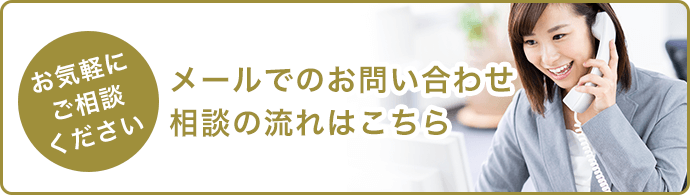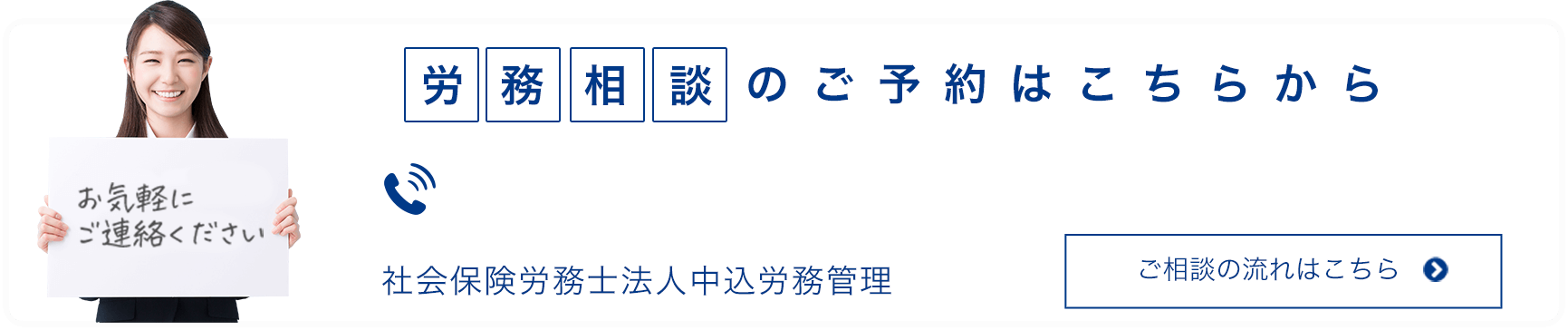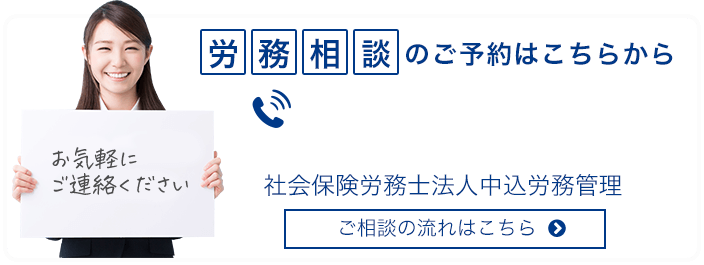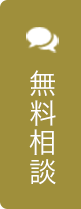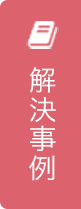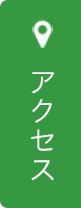人事・労務ジャーナル 2025年9月
- 2025.09.02 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
01 産休・育休中の社会保険料はどうなる?
従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。
今回は、社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終了後の対応について解説します。
02 【2025年10月施行】改正育児介護休業法を解説!
2025年10月から、育児・介護休業法が改正されます。
今回の改正では、3歳以上小学校就学前までの子どもを育てる従業員に対して、企業が柔軟な働き方を可能にする制度を整備することが義務化されます。
従来は子どもが3歳になるまでの支援が中心でしたが、今後は保育園や幼稚園に通う年齢の子どもを持つ親御さんも、より働きやすい環境が提供されることになります。
今回は、この改正の背景や目的、企業に求められる対応と準備についてご紹介します。
産休・育休中の社会保険料はどうなる?
従業員が産休や育休で休業する場合、その間の健康保険料や厚生年金保険料はどうなるのでしょうか。今回は、社会保険料免除の仕組みと手続き、免除される期間、休業終了後の対応について解説します。
産休・育休中は社会保険料が免除される
社会保険料が免除される期間は、産前産後休業を開始した月から、終了日の翌日が含まれる月の前月までです。免除は日割りではなく月単位で適用されるため、休業が月の途中で終了し復職した月は免除対象外となります。ただし、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得した場合も、当該月の保険料が免除されます。
賞与についての保険料も、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える期間の育児休業を取得した場合は免除になります。なお、免除期間も保険料を納付したものとして扱われますので、将来受け取る年金額が減額される心配はありません。
社会保険料免除の手続き方法
社会保険料の免除を受けるには、会社による申請手続きが必要です。従業員から産休・育休の申し出を受けたら、事業主は速やかに所轄の年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を提出しましょう。申請が受理されれば、その休業期間中の社会保険料は従業員・会社とも徴収が免除されます。
休業終了後の対応
従業員が復職したら、社会保険料の免除措置は終了し、会社と従業員による保険料の支払いが再開します。予定より早く復職したり、育休を延長した場合には、当初届出していた休業終了予定日を変更する手続きが必要です。会社が「産前産後休業取得者変更(終了)届」や「育児休業等取得者終了届」を提出して休業期間の変更を届け出ましょう。届出を怠ると、免除期間と実際の休業期間にずれが生じて保険料の徴収に誤りが発生する恐れがありますので注意しましょう。
産休・育休中の社会保険料免除制度は、従業員と企業双方の負担を軽減できる有益な仕組みです。制度を正しく理解し、従業員から産休・育休の申し出があった際には速やかに手続きを行いましょう。適切な対応により、従業員は安心して育児に専念でき、会社としても円滑な職場復帰を支援することができます。また、育児休業から復帰した場合の社会保険料の変更手続きについても、通常の保険料改定とは異なる取り扱いがありますので、手続き漏れがないように注意をしましょう。
【2025年10月施行】改正育児介護休業法を解説!
2025年10月から、育児・介護休業法が改正されます。今回の改正では、3歳以上小学校就学前までの子どもを育てる従業員に対して、企業が柔軟な働き方を可能にする制度を整備することが義務化されます。従来は子どもが3歳になるまでの支援が中心でしたが、今後は保育園や幼稚園に通う年齢の子どもを持つ親御さんも、より働きやすい環境が提供されることになります。
改正の背景と目的
政府は子育て中の従業員が仕事と育児を両立しやすい職場環境を整備することで、育休復帰後の離職防止や男性の育児参加促進を目指しています。特に子どもが3歳から就学前の時期は、保育園の送迎や子どもの急な体調不良などで柔軟な勤務対応が必要になる場面が多く見られます。こうした背景から、2025年10月の法改正では、この年代の子どもを育てる従業員がフルタイムで働き続けられるよう企業に新たな制度整備を求めることになりました。企業は対象従業員のために、柔軟な働き方を実現する制度を職場に導入する必要があります。
柔軟な働き方を実現するための5つの措置
改正法では、企業が選択して導入すべき柔軟な働き方の制度が5つ示されており、この中から少なくとも2つ以上を実施することが義務づけられました。
5つの制度は次のとおりです。
・始業時刻等の変更(フレックスタイム制の導入や始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ)
・月10日以上のテレワーク制度
・保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配および費用負担等)
・年10日以上の養育両立支援休暇の付与
・短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの)
企業は自社の状況に合わせてこれらの中から二つ以上を選び、社員がそのうち1つを利用できるようにしなければなりません。
企業に求められる対応と準備
企業はこの法改正に向け、2025年10月までに就業規則や社内制度の整備が必要です。まず、自社の従業員ニーズを踏まえて導入する措置を検討し、従業員代表者の意見を聴きながら制度を決定することが重要です。決定した措置は就業規則に盛り込み、必要に応じて社内規程の改定手続きを進めましょう。また、子どもが3歳になる前に対象従業員一人ひとりに制度の内容を周知し、利用希望の有無を個別に確認することも義務化されています。新制度への対応には時間がかかるため、早めに準備を始めることが大切です。
柔軟な働き方の制度を整えることで、子育て中の社員が安心して働き続けられ、人材の定着や生産性向上にもつながるでしょう。法対応にとどまらず、この機会に従業員の声に耳を傾け、子育てを皆で支える風土づくりを進めていきましょう。
-
社会保険労務士法人労務管理PLUSへの
人事と労務管理の専門家として、これまで各業種の企業さまへさまざまなサポートを提供してまいりました。顧問企業がお困りの際に「受け身」でご支援を行うだけではなく、こちらから「積極的に改善提案を行うコンサルティング業務」をその特色としております。人事労務にお悩みのある企業さまはもちろんのこと、社内環境の改善を目指したい方、また問題点が漠然としていてご自身でもはっきり把握されていない段階であっても、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。
最新のお知らせ・セミナー情報
-
- 2026.01.19 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「カスハラ対策義務化で企業が取り組むべき対応!」をお送りします❗️
-
- 2026.01.16 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「2026年以降に拡大する社会保険適用のポイント!」をお送りします❗️
-
- 2026.01.05 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 人事・労務ジャーナル 2026年1月
-
- 2025.12.22 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「割増賃金単価の正しい計算方法と注意点!」をお送りします❗️
-
- 2025.12.18 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「【2026年施行】女性活躍推進法のポイントまとめ!」をお送りします❗️