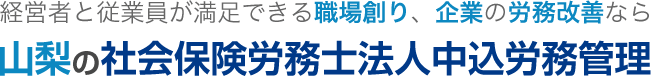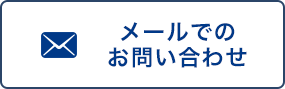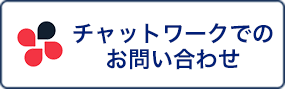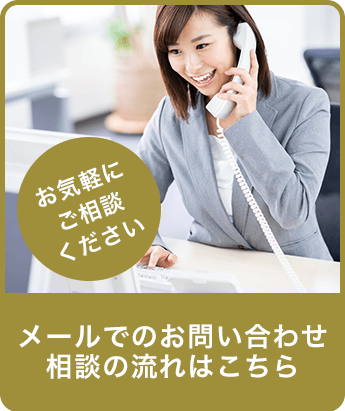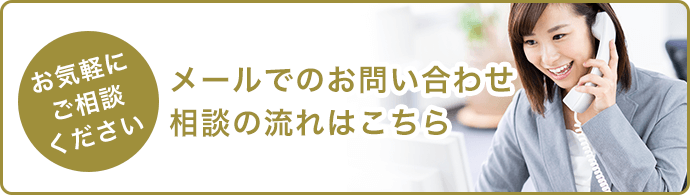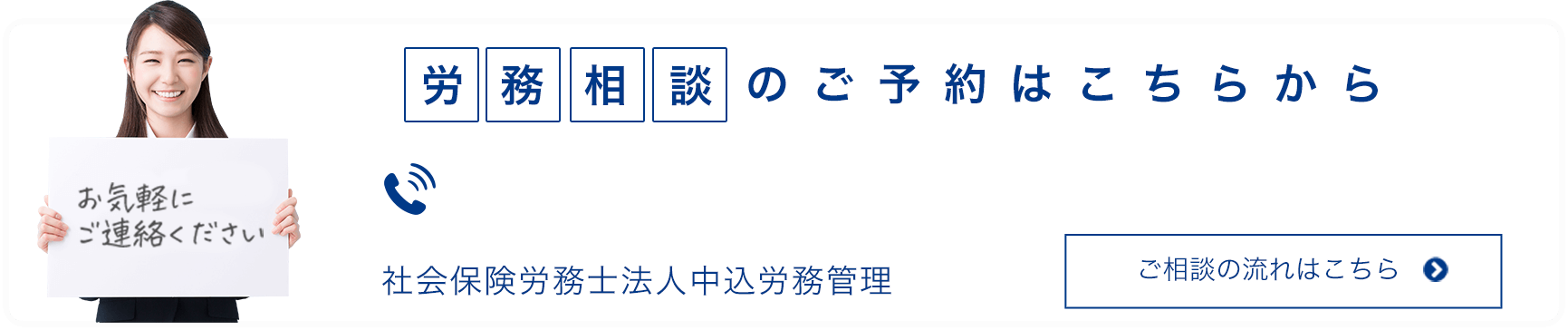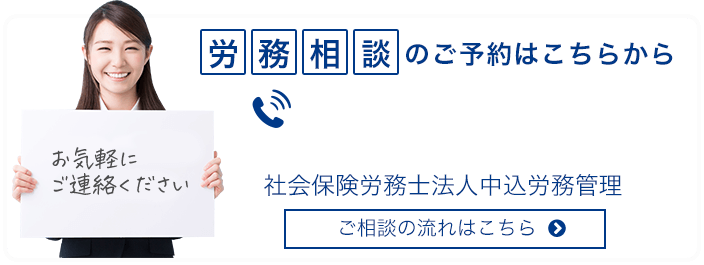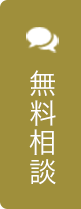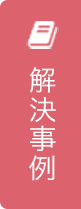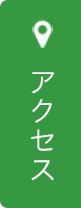人事・労務ジャーナル 2025年11月
- 2025.11.04 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
01 2025年10月から全国最低賃金引上げ!確認が必要な事項とは?
2025年10月から全国で最低賃金が引き上げられます。
今回は、この最低賃金引上げにあたり、確認しておくべきポイントをお伝えします。
02 令和7年の年末調整の改正点まとめ!
令和7年の年末調整では、税制改正に伴い大きな改正があります。
特に所得税の基礎控除額や給与所得控除が引き上げられ、新たに「特定親族特別控除」という制度も創設されました。
これら令和7年分から適用されるため、源泉徴収や年末調整の実務に影響します。今回は、この改正の主な改正ポイントを解説します。
2025年10月から全国最低賃金引上げ!確認が必要な事項とは?
2025年10月から全国で最低賃金が引き上げられます。
今回は、この最低賃金引上げにあたり、確認しておくべきポイントをお伝えします。
全国平均63円アップ!過去最大の最低賃金引上げ
厚生労働省の発表によると、2025年10月から最低賃金が全国平均で時間あたり約63円(都道府県によっては最大82円)引き上げられる見通しです。これは過去最大の引上げ幅となります。それだけ大幅な賃上げとなるため、人件費への影響も無視できません。まずは自社の所在する都道府県の新しい最低賃金額を把握しておきましょう。
アルバイトだけでなく月給者も最低賃金に注意
最低賃金はパートやアルバイトなど時給制の労働者だけでなく、月給制の正社員にも適用されます。月給の場合は、月給額を1か月の所定労働時間で割った金額が時給換算額となり、この金額が最低賃金を下回っていないか確認が必要です。例えば基本給が月20万円で、1か月の所定労働時間が168時間の場合、時給換算額は約1,190円となり、東京や神奈川の新しい最低賃金(いずれも1,200円超)を下回ります。最低賃金割れが生じないよう、全ての従業員の給与水準をチェックしましょう。また、月給額には皆勤手当や家族手当・通勤手当は含みませんので注意が必要です。
最低賃金改定の発効日は地域ごとに異なる
今年度から最低賃金の改定時期が都道府県ごとに異なる点にも注意が必要です。多くの地域では10月上旬から中旬に新しい最低賃金が発効しますが、遅い地域では2026年3月31日といった時期に引き上げが行われる地域もあります。自社の所在地では新しい最低賃金がいつから適用されるのか、事前に確認しておきましょう。
最低賃金の大幅引上げに伴い、従業員の賃金が新しい基準を下回らないかどうか、早めに確認しておくことが大切です。最低賃金の遵守は法律上の義務であり、違反すると従業員から未払い分を請求されたり、罰則の対象となる可能性もあります。そうならないよう、必要に応じて基本給や時給額の見直しを行い、早めに引上げに対応しましょう。また、都道府県ごとの発効日も確認し、計画的に準備を進めれば、スムーズに最低賃金改定に対応できるでしょう。
令和7年の年末調整の改正点まとめ!
令和7年の年末調整では、税制改正に伴い大きな改正があります。特に所得税の基礎控除額や給与所得控除が引き上げられ、新たに「特定親族特別控除」という制度も創設されました。これら令和7年分から適用されるため、源泉徴収や年末調整の実務に影響します。今回は、この改正の主な改正ポイントを解説します。
基礎控除額の引き上げ
基礎控除額は従来一律48万円でしたが、令和7年分から所得に応じて段階的となり、低所得者の場合は控除額が最大95万円に引き上げられました。これにより、パート収入のみで所得が約132万円以下の方などは、税負担が軽くなります。
給与所得控除の引き上げ
給与所得控除も見直され、最低額が55万円から65万円に引き上げられました。誰でも一律に控除が10万円増えるため、その分手取り収入が増えます。
扶養親族・配偶者控除の所得条件緩和
基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、扶養親族や配偶者が控除対象となる所得条件も緩和されました。従来は合計所得48万円以下(給与収入で年約103万円以下)までしか認められませんでしたが、2025年分からは58万円以下(同約123万円以下)まで認められます。「103万円の壁」が約123万円に引き上げられた形です。その結果、年収が103万円を少し超える程度(123万円未満)の配偶者や子どもも、新たに控除対象となります。
特定親族特別控除の創設
大学生などのお子さんがいる場合に適用できる新しい所得控除が創設されました。アルバイト収入が年103万円を超えると扶養控除を受けられなくなるケースでも、この控除により一定の収入まで段階的に所得控除が適用されます。対象親族1人につき最大63万円の控除を受けられ、子どもの年収が約188万円を超えると適用されません。年末調整でこの控除を受けるには、新たに『給与所得者の特定親族特別控除申告書』を提出してもらう必要があります。
令和7年の税制改正により、年末調整の計算方法や必要な手続きが大きく変わります。改正内容を正しく把握し、従業員から提出される申告書類に新しい控除額や控除対象の有無が正しく反映されているか確認することが大切です。新設された控除に該当する社員がいる場合は、必要な申告書の提出漏れがないよう注意しましょう。
-
社会保険労務士法人労務管理PLUSへの
人事と労務管理の専門家として、これまで各業種の企業さまへさまざまなサポートを提供してまいりました。顧問企業がお困りの際に「受け身」でご支援を行うだけではなく、こちらから「積極的に改善提案を行うコンサルティング業務」をその特色としております。人事労務にお悩みのある企業さまはもちろんのこと、社内環境の改善を目指したい方、また問題点が漠然としていてご自身でもはっきり把握されていない段階であっても、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。
最新のお知らせ・セミナー情報
-
- 2026.02.04 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「労働基準法の改正議論を解説!企業が今から備えるポイント!」をお送りします❗️
-
- 2026.02.03 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 人事・労務ジャーナル 2026年2月
-
- 2026.01.19 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「カスハラ対策義務化で企業が取り組むべき対応!」をお送りします❗️
-
- 2026.01.16 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 「2026年以降に拡大する社会保険適用のポイント!」をお送りします❗️
-
- 2026.01.05 お知らせ・セミナー情報コラム事務所通信
- 人事・労務ジャーナル 2026年1月